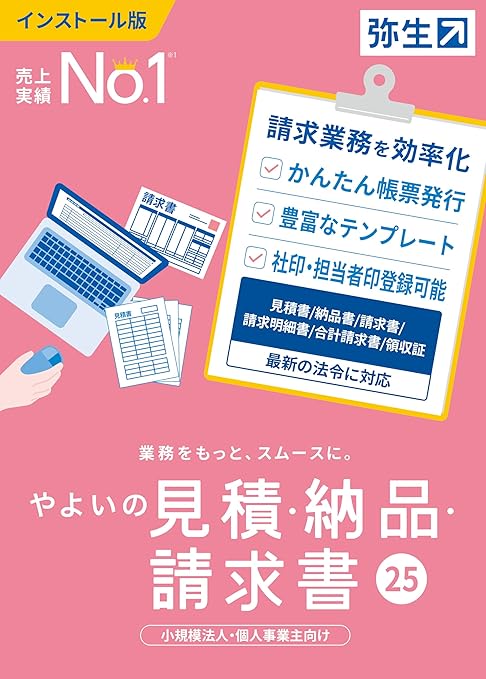こんにちは。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
2025年8月。連日の猛暑が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
最近、小規模事業者の経営者の方々、特にB to Bビジネスを展開されている方から、ITやデジタル化に関するご相談が増えていると感じています。
その背景には、Windows 10のサポート終了が近づいていることや、コロナ禍を経て業種を問わずデジタル化が急速に進んだことがあるでしょう。
クライアントや取引先から「デジタルを活用した業務運用に切り替えてほしい」と要請され、これまでIT導入に躊躇していた方も、いよいよ対応が避けられなくなってきているのではないでしょうか。
もちろん、コンシューマー向けの事業者の方々はコロナ禍でネット販売やECサイトを導入された方も多くいらっしゃいますし、スタートアップのように最初からWebやITを前提にビジネス展開されている方もおられます。
ただ、特に最近はB to Bの事業で対面営業が中心だった業種の皆さまにも、デジタル導入の波が確実に押し寄せている印象です。
目次
業務用ソフト(オンプレミス型)とクラウドサービス(SaaS)の違い
ご相談を受ける中で「クラウドサービスって便利そうだけど、これまでのパソコンにインストールするソフトと何が違うの?」というご質問がよくあります。
ここで、両者の特徴やメリット・デメリットを簡単に整理してみます。
1.パソコンにインストールして使うソフトウェア(オンプレミス型)

特徴
- ソフトウェアを自社のパソコンやサーバーに直接インストールして運用します。
- データも基本的に自社内で保存・管理します。
メリット
- インターネット接続がなくても利用できる場合が多い
- ほとんどの場合には、ソフトウェアの買い切りモデルであるため、売上の多い年度で購入するなどの経費コントロールができる
- 難易度が高いが、カスタマイズ性が高く、自社の業務フローに細かく合わせやすい
デメリット
- 導入や運用にかかるコストが高い(初期費用、保守・管理コストなど)
- バージョン管理やアップデート作業が手間
- リモートワークや外部からの利用が難しい
- 災害や機器故障時の復旧も自社で対応が必要
2. クラウドサービス(SaaS)
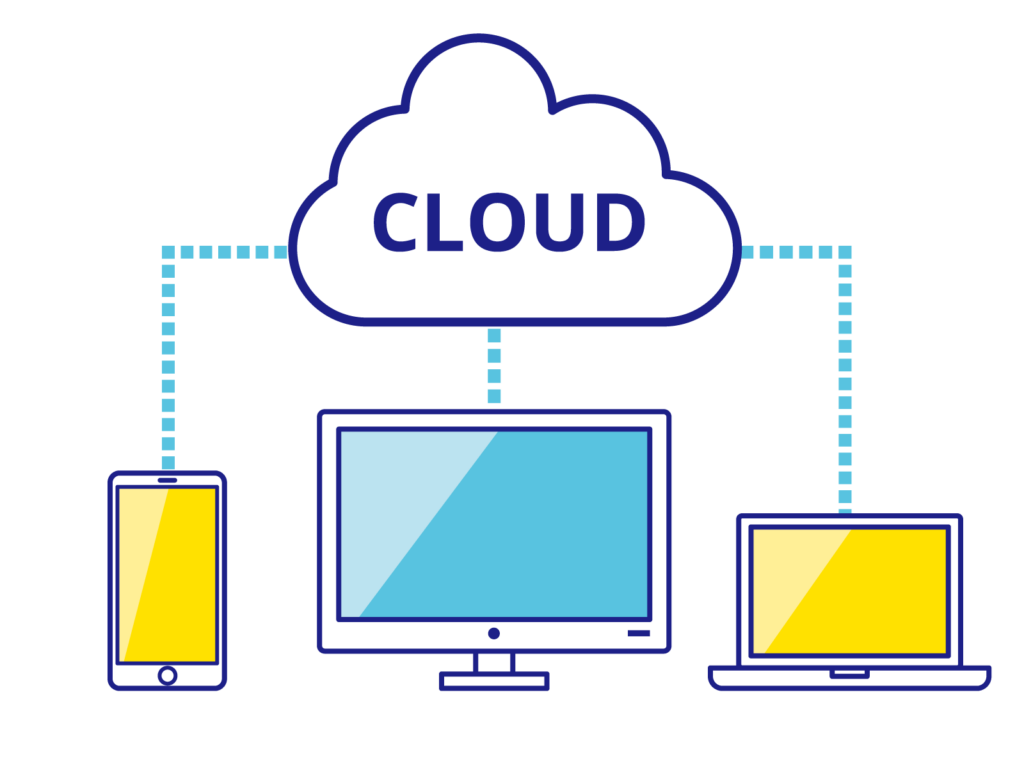
特徴
- インターネット経由でサービスを利用し、ソフトウェアやデータはクラウド上に保存されます。
メリット
- 導入が簡単で、すぐに使い始められる
- 初期費用を抑えられ、月額や年額課金で柔軟に利用できる
- 常に最新バージョンを自動で利用可能
- どこからでもアクセスでき、リモートワークにも最適
- 利用人数や機能を簡単に増減できる
デメリット
- インターネット接続が必須
- カスタマイズの自由度はベンダーが提供する範囲に限られる
- データ管理が外部依存となるため、セキュリティ・コンプライアンスの確認が必要
- サービス終了や仕様変更のリスクがある
- サービス全体に障害が発生した場合、全ユーザーに影響が及ぶ可能性
具体例:見積・請求書作成システムの場合
中小事業者でも利用頻度の高い「見積・請求書作成システム」を例に、両者の違いを解説します。
例えば弥生株式会社では、
- 「やよいの見積・納品・請求書 25」(オンプレミス型ソフト)
- クラウド請求書作成ソフト「Misoca」(SaaS)
という2つのタイプの製品が提供されています。
どちらも見積書・納品書・請求書の作成、印刷、PDF出力や会計ソフトとの連携など、基本的な業務機能は共通です。
私のおすすめはクラウド型「Misoca」
特別な事情がなければ、多くの中小事業者さまにはクラウドサービス型の「Misoca」をおすすめしています。
理由は次のような、クラウドならではのメリットがあるからです。
1. スモールスタートが容易で、規模の変化に柔軟に対応できる
最初は社長お一人でスタートし、事業拡大に伴い家族やパート従業員の方を雇用するフェーズに入った時、インストール型のソフトはサーバー構築など拡張が難しくなりがちです。
クラウドサービスであれば、アカウントを追加するだけで簡単に対応でき、ITの専門知識がなくてもスムーズに業務を拡張できます。
2. 外部専門家との連携が簡単
会計事務所やIT専門家との連携も、クラウドサービスであればアカウントを発行するだけで遠隔サポートが可能です。
インストール型だとデータのやり取りや同期が手間ですが、クラウドならデータ共有や操作もリアルタイムで行えます。また、トラブルが起きた際にもインストール型のソフトウェアの場合には、現地でしか作業できないことがありますので、業務停滞を招く可能性がありますが、クラウドの場合には離れた場所からでもエンジニアが状況を確認できます。
3. アップデートやバックアップの運用負担が軽減
ソフトウェアは定期的なアップデートやバックアップが欠かせません。オンプレミス型だとこれらを自力で対応する必要があり、知識や手間が求められます。
クラウドサービスなら、アップデートもバックアップもベンダー側で自動的に実施されるため、日々の運用負担を大幅に減らせます。
※全てのクラウドサービスが同じ運用をしているとは限りません。導入前に内容をよくご確認ください。
4. 解約・契約更新には注意
クラウドサービスは月額・年額契約が主流です。
契約更新を忘れるとデータが削除される場合もあるので、自動更新設定や定期的な確認をおすすめします。
まとめ
日本国内では高品質なインターネット回線が比較的安価で利用できるため、クラウドサービス導入のハードルは年々下がっています。
クラウドサービスは利用規模に応じて料金が変動しますが、小規模事業者でも低コストで豊富な機能を活用できます。
今後ますます進むデジタル化の流れにのって、ITやクラウドサービスの導入を前向きに検討されてはいかがでしょうか。
弊事務所でもクラウドサービス導入のご相談・サポートを承っておりますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。